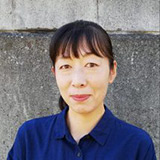火災保険の水災(水害)への補償は必要?
補償内容や適用条件を解説

補償内容や適用条件を解説

火災保険は、火災だけでなく、風水災等の自然災害による損害も広くカバーできる保険です。近年では台風や豪雨による被害のニュースを見聞きする機会も多く、火災保険の水災(水害)補償について気になっている人も多いのではないでしょうか。一方で、火災保険の保険料を抑えるため、水災補償を外すことを検討している人もいるかもしれません。
火災保険の水災補償は、地域や住まいの環境等によって必要性が異なります。河川から離れた地域でも水害リスクが高い場合もあるため、火災保険の水災補償については慎重に判断することが大切です。
ここでは、火災保険の水災補償について、補償内容や適用条件、必要性を判断するポイント等について解説します。
この記事のポイント
- 水災(水害)は、日本の地理・気象条件から発生リスクが高い
- 火災保険は任意で水災補償をセットできることが多い
- 水災補償の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3通り
- ハザードマップや過去の災害等を確認し、水災補償の必要性を判断することが大切
水災(水害)とは?
水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨等、水に起因する自然災害による損害のことです。日本は、国土の約7割が山地や丘陵地であり、急勾配の河川が多く存在します。都市の多くは海や河川の水位より低い土地に形成されているため、河川から水があふれたり堤防が決壊したりすると、大規模な水災に発展してしまう可能性も少なくありません。
さらに、近年の地球温暖化の影響により、局地的な豪雨の発生頻度等が高まり、大規模な浸水や土砂災害が各地で発生しています。
また、水災は河川の近くだけで起こるとは限りません。都市部等では、集中豪雨による雨が河川等へ排水しきれなくなり、下水道管や水路からあふれ出る「内水氾濫」も多く発生しています。こうした水災のリスクは今後ますます高まるでしょう。
水災の発生時期は、6~7月の梅雨シーズンや8~9月の台風シーズン等に集中しやすい傾向があります。ゲリラ豪雨や線状降水帯による集中豪雨には特に注意が必要です。
なお、実際の災害例として、2018年7月に発生した西日本豪雨では、床上浸水8,567棟、床下浸水2万1,913棟等という大規模な被害がありました。
このように、一度の災害で数万棟に及ぶ被害が発生するケースもあります。特に近年は線状降水帯やゲリラ豪雨等の突発的な大雨が頻発しており、想定外の場所で浸水被害が起こることも珍しくありません。
※出典:国土交通省「平成30年7月豪雨」
https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2018/20180713/20180713.html
水災リスクに備えるなら火災保険の「水災補償」
水災リスクに備える方法のひとつが、火災保険の水災補償です。火災保険は、火災等によって建物や家財に生じた損害を補償する保険で、火災だけでなく水災による損害も補償されます。
ただし、水災補償は、すべての火災保険に自動でセットされているわけではないことに注意が必要です。水災補償が必要な場合は、火災保険の加入時にオプションとして追加するか、あらかじめ基本補償に水災補償が組み込まれている保険商品を選ぶことになります。
水災補償の有無や条件は保険会社や保険プランによって異なるため、加入時にしっかり内容を確認することが大切です。
水災に対する補償内容
火災保険に水災補償をセットしていると、水災によって一定以上の損害を受けた場合に、保険金を受取れます。水災補償の対象となる損害の例は、以下のとおりです。
<水災補償の対象となる損害の例>
- 台風によって近隣の川が氾濫し、住まいが床上浸水した
- 集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込んだ
- 豪雨の影響で地盤がゆるみ、建物が傾いたり、居住不可能になったりした
- 高潮による床上浸水で、壁紙の張り替えが必要になった
ただし、火災保険は、加入時に補償対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3通りから選択する必要があり、水災補償の対象もこの範囲内に限定されます。例えば、「建物のみ」を選択した場合は、水災で家財に損害が生じても保険金を受取ることはできません。
水災補償が適用される条件
火災保険における水災補償は、どのような損害でも必ず補償されるわけではありません。保険金を受取るには、一定の条件を満たす必要があります。
適用条件は保険会社によって異なる場合もありますが、一般的には、以下の(1)(2)いずれかを満たした場合に保険金を受取れます。
<水災補償の適用条件>
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって
(1)保険の対象である建物や家財に評価額(家財の場合は再調達価額)の30%以上の損害が発生した場合
(2)床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水し、保険の対象が損害を受けた場合
原則として、これらの基準を下回る軽度の浸水や損害では保険金が受取れません。そのため、補償内容をしっかりと理解することが大切です。
なお、受取る保険金の金額は、損害の額から免責金額を引いた額となります。免責金額は保険証券等に記載されているので確認しておきましょう。
火災保険に水災補償は必要?
水災補償が必要かどうかは、住まいの地域や立地条件等によって異なります。火災保険に加入する時には、「水災補償なし」という選択も可能なため、水災補償をセットするか迷う人もいるかもしれません。
国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」を見ると、住まいの地域の水害リスクを視覚的に確認できます。川や海、用水路の近く、あるいは標高が低く水が集まりやすい場所、過去に浸水の被害が出た地域等は、今後も同様の災害に見舞われる可能性もあります。
また、水災補償を検討する際には、ハザードマップに現れない内水氾濫等のリスクについてもしっかり確認することが大切です。
内水氾濫は、地面がアスファルト等で舗装された都市部で起こりやすく、マンホールから水が噴出したり、トイレや風呂場等から下水が逆流したりして住宅が浸水する可能性もあります。
自治体によっては「内水ハザードマップ」を作成している場合もあるので、住まいの自治体のWebページを確認しましょう。
※出典:国土交通省「近年の降雨及び内水被害の状況、下水道整備の現状について」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001320996.pdf
水災補償が受けられない損害
水災補償は水による自然災害をカバーする補償ですが、水に関する損害のすべてが補償対象になるわけではありません。ここでは、水災補償では対応できない代表的な損害について解説します。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害
水による損害であっても、原因が地震や噴火、またはそれらによって発生した津波である場合は、水災補償の対象にはなりません。これらの災害に備えるには、別途、地震保険への加入が必要になります。
なお、地震保険は、単独での加入はできず、必ず火災保険とセットでの加入となります。すでに火災保険に加入している場合は、保険期間の途中からでも地震保険への加入が可能です。
地震保険については、以下の記事をご覧ください。
地震保険は入るべき?必要性や補償内容、検討のポイントについて解説
「水ぬれ」「漏水」による損害
水が原因で損害が発生しても「水ぬれ」「漏水」に該当する場合は、水災補償の対象外です。自然災害によるものではなく、建物内の設備や配管のトラブル等によって発生する損害であることから、水災補償ではなく、火災保険の「水ぬれ」の補償対象となります。
「水ぬれ」「漏水」の損害の例は以下のとおりです。
<「水ぬれ」「漏水」による損害の例>
- 排水管が詰まって部屋が水浸しになった
- マンション上階からの水漏れにより、部屋が水浸しになった
- 洗濯機のホースが外れて水が床に広がった
自然災害による水災と、設備不良等による水ぬれでは補償の種類が異なります。契約内容をしっかりと確認し、必要に応じて両方の補償を検討することが大切です。
風・雹(ひょう)・雪による損害
風や雹(ひょう)、雪等による損害は、水による直接的な損害とは性質が異なるため、水災補償の対象外です。なお、これらは火災保険の「風災・雹(ひょう)災・雪災」の補償対象となります。
風・雹(ひょう)・雪による損害の例は、以下のとおりです。
<風・雹(ひょう)・雪による損害の例>
- 強風で屋根瓦が飛ばされた
- 雹(ひょう)で外壁や自動車が傷ついた
- 大雪の重みでベランダの屋根が崩れた
ただし、雪解け水によって河川が氾濫して洪水が発生し、それによって損害を受けた場合は、水災補償の対象です。
「風災・雹(ひょう)災・雪災」の補償は、火災保険の基本補償に含まれているケースが一般的ですが、保険会社や保険プランによって補償内容や適用条件は異なる場合があるため、事前に確認すると安心です。
火災保険の補償内容については、以下の記事をご覧ください。
火災保険の補償内容・補償範囲はどこまで?保険料を抑えるポイントも解説
火災保険の内容を確認して住まいの水災リスクに備えよう
日本の多くの都市は、海や河川の水位より低い土地に形成されており、水災リスクには注意が必要です。さらに、近年の気候変動の影響等により、水災リスクはますます高まっていくと考えられています。河川から離れた地域であっても、内水氾濫等、思わぬ形で水災が発生する可能性は十分考えられます。水災の損害に備えるには、火災保険に水災補償をセットすることを検討するといいでしょう。
住まいに合った補償を選びたい場合は、保険の専門家に相談するのがおすすめです。「ほけんの窓口」では、火災保険のプランに関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。火災保険の水災補償について検討したい場合も、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。
- ※特約の名称や補償内容は保険会社ごとに異なります。
- ※当ページでは火災保険に関する一般的な内容を記載しています。個別の保険商品等の詳細については保険会社及び取扱代理店までお問い合わせください。
(2025年6月承認)B25-200478
火災保険の水災補償についてよくある質問
火災保険の水災補償について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。
- 水災とはどのような災害ですか?
- 水災(水害)とは、台風、暴風雨、豪雨等、自然の水の力によって引き起こされる災害のことです。日本は国土の約7割が山地や丘陵地であること、都市の多くは海や河川の水位より低い土地に形成されていること等から、全国的に水災リスクが高いといわれています。また、近年の気候変動の影響により、台風や豪雨の発生頻度等が増加すると予測されています。都市部等では、「内水氾濫」も多く発生しているため、注意が必要です。
- 火災保険の水災補償はどのような場合に補償が受けられますか?
- 火災保険の水災補償をセットしていれば、水災によって一定以上の損害を受けた場合に補償を受けられます。具体的には、「保険の対象である建物や家財に評価額(家財の場合は再調達価額)の30%以上の損害が発生した場合」または「床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水し、保険の対象が損害を受けた場合」に、保険金を受取れることが一般的です。
- 火災保険に水災補償は必要ですか?
- 水災補償の必要性は、住まいの地域の水災リスクによって異なります。水災リスクが高い地域や、過去に大規模な水災が起こった地域に住んでいる場合、水災補償の必要性は高いといえます。また、内水氾濫等のリスクについても注意が必要です。自治体の「内水ハザードマップ」等をチェックし、慎重に判断しましょう。
- 水災補償の対象外の損害はどのようなものがありますか?
- 水災補償の対象にならない損害の例としては、「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害」「水ぬれ・漏水による損害」「風・雹(ひょう)・雪による損害」等が挙げられます。地震による損害に備えるには地震保険に加入する必要があります。また、「水ぬれ・漏水による損害」は火災保険の「水ぬれ」の補償対象、「風・雹(ひょう)・雪による損害」は「風災・雹(ひょう)災・雪災」の補償対象です。
監修者プロフィール
黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
FPサテライト株式会社 流山サテライトオフィスマネージャー
FPサテライト株式会社 流山サテライトオフィスマネージャー
大学院修了後、IT企業や通信事業者でセールスエンジニア兼企画職として働く。保険や税制の執筆業務を得意とし、年間約150本の執筆・監修を行う。通信事業者での経験を活かし、通信費削減に関する情報提供にも力を入れる。地域とのつながりを重視し、3人の子育てをしながら「地域×FP」をテーマに空き家問題や創業支援に取り組む。