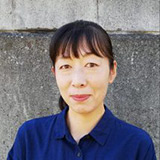地震保険はマンションでも必要?
補償範囲や保険料の目安について解説

補償範囲や保険料の目安について解説

地震大国と呼ばれる日本では、いつ、どこで大きな地震が起こるかわかりません。被災後の生活を立て直すためには、地震保険で備えておくことが大切です。ただ、マンションを所有している場合、「マンションは耐震性に優れているから地震で大きな被害は受けないのでは?」「マンションなら地震保険は必要ないだろう」等と考える人もいるかもしれません。
「マンションだから大丈夫」という漠然としたイメージだけで地震保険に未加入のままでいると、いざという時に後悔することになってしまう可能性があります。では、実際のところ、マンションに地震保険は必要なのでしょうか。
ここでは、マンションを所有している人に向けて、地震保険の必要性や地震保険の補償範囲、保険料の目安の他、マンションの地震保険への加入を検討する際のポイント等について解説します。
この記事のポイント
- 地震保険は、地震等を原因とする建物や家財の損害を補償する保険
- マンションでも地震保険の必要性が高い
- 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定できる
- マンションの地震保険への加入は、マンションの構造や地震発生リスク、自身の資産状況等を考慮して判断することが大切
地震保険とは地震等による建物や家財の損害を補償する保険
地震保険とは、地震等を原因とする建物や家財の損害を補償する保険です。具体的には、地震や噴火、またはこれらによる津波(以下「地震等」)を原因とする建物と家財の損害が補償されます。
地震等は、いつどこで起こるかといった予測が困難な上、被害が発生した時の影響は甚大かつ広範囲に及びます。もし地震等で建物が被害を受けた場合、生活を立て直すためには多額の費用が必要になるでしょう。地震保険の目的は、このような地震等による被災者の当面の生活と生活再建を支えることです。
地震保険は、政府と損害保険会社が「地震保険に関する法律」に基づいて共同で運営する、公共性の高い保険です。そのため、建物の所在地(都道府県)や構造等の条件が同じであれば、どの保険会社で加入しても、補償内容や保険料は同じです。また、大地震が起こったとしても巨額な保険金の支払いに支障のないよう、保険金の支払責任の一部を政府が負うこととしています。
なお、地震保険は単独での加入はできず、必ず火災保険とセットでの加入となります。すでに加入している火災保険に地震保険をセットしていない場合は、保険期間の途中からでも地震保険への加入が可能です。
地震保険については、以下の記事をご覧ください。
地震保険はいらない?必要性や補償対象、保険料、割引等を解説
マンションにも地震保険は必要
所有しているのが戸建てではなくマンションであっても、地震等やそれらを原因とする火災に備えるために、地震保険は必要です。
マンションを所有している人のなかには「近年のマンションは耐震性に優れているから、地震でもそれほど大きな被害を受けることはないだろう」と考えている人もいるかもしれませんが、地震に強いといわれるマンションであっても被災した例は少なくありません。
例えば、阪神・淡路大震災や東日本大震災では、多くのマンションに被害が及びました。倒壊しなかったマンションでも、壁や天井、室内の家財に大きな被害を受けています。室内の修繕や新しい家具・家電の購入、住宅ローンの支払い等、経済的なダメージは少なくありません。
また、地震等の揺れによって家具が転倒、落下し、それらが火元となって火災が発生することもあります。
通常の火災による損害であれば火災保険で補償を受けられますが、地震等による火災や倒壊等の損害は、火災保険の補償対象外となるため、地震保険でカバーしなければなりません。
マンションであっても、いつ起こるかわからない地震等やそれに伴う火災のリスクに備えるには、地震保険の必要性が非常に高いといえます。なお、地震保険で受取れる保険金の使途は自由なので、引越しにかかる費用にあてることも可能です。
マンションの専有部分と共用部分の地震保険
区分所有建物であるマンションには、「専有部分」と「共用部分」という大きく分けて2つの区域があり、地震保険では一般的にそれぞれ加入者が異なります。専有部分とは、住戸として区分所有者(入居者)が個別に所有する範囲で、居住スペースのことです。一方の、共用部分とは、エントランスや廊下、エレベーター、外壁等の住民全員が共同で使用する場所のことを指します。
マンションの入居者が個別に地震保険に加入する必要があるのは、専有部分の建物と家財になります。地震等やそれに伴う火災により、専有部分の設備や家財に被害を受けた場合、地震保険に加入していなければ、かかる費用は全額自己負担です。
なお、一般的にマンションの共用部分については、管理組合が地震保険に加入します。ただし、管理組合が地震保険に加入しているかどうかはマンションによって異なるため、事前に確認が必要です。もし管理組合が地震保険に加入していないと、地震等で共用部分が被害を受けた場合、修繕積立金だけではカバーできないかもしれません。修繕に必要な資金が足りず、住民に追加負担が発生したり、そのマンションに住めなくなったりする可能性もあります。
地震保険料の目安
地震保険の保険料は、建物の所在地(都道府県)や構造等によって決まります。都道府県で保険料が変わるのは、場所によって地震等のリスクが異なるからです。また、建物の構造区分は、耐火性能や準耐火性能等を有する建物(イ構造)とイ構造以外の建物(ロ構造)で区別され、構造区分ごとに適用される保険料率が変わります。なお、前述したように、建物の所在地(都道府県)や構造等の条件が同じであれば、どの保険会社で加入しても、補償内容や保険料は同じです。
地震保険の保険料は、これまで何度か改定が行われていますが、2025年3月現在、以下のようになっています。
■地震保険の年間保険料(保険期間1年、地震保険金額1,000万円あたり、割引適用なしの場合)
| 建物の所在地(都道府県) | 建物の構造 | |
|---|---|---|
| イ構造 | ロ構造 | |
北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県 | 7,300円 | 1万1,200円 |
宮城県・福島県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県 | 1万1,600円 | 1万9,500円 |
茨城県・徳島県・高知県 | 2万3,000円 | 4万1,100円 |
埼玉県 | 2万6,500円 | |
千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 | 2万7,500円 | |
地震保険の割引制度
地震保険には、住宅の免震・耐震性能等に応じた4つの割引制度があります。建物が、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引のいずれかの条件に該当する場合、地震保険の保険料が10~50%割り引かれます。割引制度と割引率の詳細は以下のとおりです。
なお、各割引制度の重複適用はできません。
■地震保険の割引制度
| 割引制度 | 割引率 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 50% | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)に基づく免震建築物の基準に適合する建物およびその収容家財 |
| 耐震等級割引 | 耐震等級3:50% | 「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊防止等)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物およびその収容家財 |
| 耐震等級2:30% | ||
| 耐震等級1:10% | ||
| 耐震診断割引 | 10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす建物およびその収容家財 |
| 建築年割引 | 10% | 1981年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財 |
マンションの地震保険で受取れる保険金
地震保険の保険金額は、セットで加入する火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額です。
また、地震保険は、どのような場合でも設定した保険金の全額が受取れるわけではありません。地震保険で受取れる保険金額は、建物や家財の損害の程度によって決まります。損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という4段階に区分されており、それぞれ100%、60%、30%、5%といった保険金額の一定の割合を受取れます。一部損に満たない場合や、損害が門や塀、垣のみの場合等は、保険金を受取ることはできません。
損害の程度の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって行われます。認定の基準は、下表のとおりです。
■損害の程度と受取れる保険金の割合・地震保険損害認定基準
| 損害の程度 | 支払われる保険金の割合 | 地震保険損害認定基準(建物については次のいずれかの場合) 上段:建物 下段:家財 |
|---|---|---|
| 全損 | 保険金額の100% (時価額が限度) | 1. 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上の場合 2. 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の70%以上の場合 |
| 家財の損害額が、家財の時価額の80%以上となった場合 | ||
| 大半損 | 保険金額の60% (時価額の60%が限度) | 1. 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満の場合 2. 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満の場合 |
| 家財の損害額が、家財の時価額の60%以上80%未満となった場合 | ||
| 小半損 | 保険金額の30% (時価額の30%が限度) | 1. 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満の場合 2. 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満の場合 |
| 家財の損害額が、家財の時価額の30%以上60%未満となった場合 | ||
| 一部損 | 保険金額の5% (時価額の5%が限度) | 1. 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満の場合 2. 地震等によりその建物の損害が一部損に至らない場合で建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 |
| 家財の損害額が、家財の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
※時価額とは、同等のものを建て直しまたは新たに購入するために必要な金額から、「使用による消耗分」を差し引いた金額をいいます。
マンションの場合は、まず、建物全体の損害認定を行い、その損害認定が、共用部分、専有部分にも同様に適用されます。建物全体の損害認定を行う上でポイントになるのが、柱、梁、外壁等の主要構造部が受けた損害の程度です。共用部分が全損と認定されれば、専有部分も全損となります。もし共用部分が小半損、専有部分が一部損だった場合は、住戸である専有部分も共用部分と同様に小半損と認定されます。
ただ、場合によっては、専有部分のほうが共用部分より損壊が激しいこともあるかもしれません。そのような場合は、加入先の保険会社に、個別に再審査を依頼することが可能です。
マンションの地震保険を検討する際のポイント
マンションの地震保険を検討する際には、住んでいるマンションの構造や、居住地の地震発生リスク、自身の資産状況等を考慮して判断することが大切です。それぞれ意識したいポイントを以下に挙げます。
マンションの構造
地震保険について検討する時は、住んでいるマンションの構造を確認することが大切です。マンションが耐震構造、免震構造、耐火構造になっていれば、地震が起きてもそれほど大きな被害は受けないかもしれません。また、1981年6月1日以降に建てられたマンションであれば、震度6強~7程度の地震でも倒壊・崩壊しないとされる「新耐震基準」が適用されています。ただし、地震等でマンションが倒壊しなくても、被災しないとは限りません。
例えば、地震等が起こった時の建物の揺れやすい周期は建物の高さによって異なります。高層マンションは、一戸建て等に比べて長時間にわたり大きく揺れる可能性があります。同じマンションでも、低層階よりも高層階のほうがより大きく揺れる傾向があり、損害が大きくなる可能性も否定できません。
居住地の地震発生リスク
マンションの地震保険を検討する際は、居住地の地震発生リスクもチェックしておきたい項目のひとつです。地震をはじめとする自然災害の発生リスクは、地域によって異なります。もし頻繁に地震が起こっている地域や、今後大規模な地震が起こる可能性があるといわれている地域に住んでいるのであれば、地震保険の必要性は高いと考えられます。
居住地の地震発生リスクを確認するには、「ハザードマップ」を参考にするのもひとつの方法です。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」を見ると、住まい近辺の災害リスクを調べることができます。ハザードマップは最新情報を基に更新されるため、定期的にチェックすることをおすすめします。
自身の資産状況
マンションの地震保険を検討する際は、自身の資産状況について、あらためて確認しておきましょう。地震等による被害を受けても、自力で生活を立て直すだけの資産の余裕があれば、地震保険に加入しなくても問題ないかもしれませんが、大規模な地震が起こって避難生活や引越しを余儀なくされる等、想像以上に経済的な負担が大きくなる可能性もあります。資産に余裕がなかったり、住宅ローンがのこっていたりする場合は、地震保険に加入しておいたほうが安心です。
マンション住まいの場合も地震保険を検討しよう
マンション住まいの場合でも、地震等で大きな被害を受ける可能性は十分考えられます。火災保険だけに加入していても、地震等による火災や倒壊等の損害はカバーできません。マンションだからといって過信せず、もしもに備えて地震保険への加入を検討しましょう。なお、地震保険は単独での加入ができず、火災保険とセットで加入しなければなりません。
地震保険への加入や保険金の設定に迷ったら、保険の専門家に相談するのがおすすめです。
「ほけんの窓口」では、地震保険に関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。地震保険について検討したい場合は、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。
- ※補償内容は保険会社ごとに異なります。
- ※当ページでは地震保険に関する一般的な内容を記載しています。個別の保険商品等の詳細については保険会社および取扱代理店までお問い合わせください。
(2025年3月承認)B24-104087
マンションの地震保険についてよくある質問
マンションの地震保険について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。
- 地震保険とはどのような保険ですか?
- 地震保険とは、地震等による建物や家財の損害を補償する保険です。地震は予測が困難な上、被害が発生した時の影響は甚大かつ広範囲に及びます。地震等で建物等が被害を受けた場合、生活を立て直すためには多額の費用が必要になります。地震保険の目的は、このような地震等による被災者の当面の生活と生活再建を支えることです。
- マンションにも地震保険が必要な理由は?
- マンションにも地震保険が必要な理由は、地震等やそれらを原因とする火災に備えるためです。通常の火災による損害であれば火災保険でカバーできますが、地震等による火災や倒壊等の損害は、火災保険の補償対象には含まれていません。また、居住スペースである専有部分は居住者が個別に地震保険に加入する必要があります。
- マンションの地震保険で受取れる保険金はどのくらい?
- 地震保険の保険金額は、セットで加入する火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額です。受取れる保険金額は、建物や家財の損害の程度によって決まります。損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という4段階に区分されており、認定された区分に応じて保険金額の一定の割合が受取れます。
- マンションの地震保険を検討する際のポイントは?
- マンションの地震保険を検討する際は、住んでいるマンションの構造や、居住地の地震発生リスク、自身の資産状況等を考慮して判断することが大切です。特に、揺れやすい高層階や地震発生リスクの高い地域のマンションに住んでいる場合は、地震保険でリスクに備える必要性が高いといえるでしょう。
監修者プロフィール
黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
FPサテライト株式会社 流山サテライトオフィスマネージャー
FPサテライト株式会社 流山サテライトオフィスマネージャー
大学院修了後、IT企業や通信事業者でセールスエンジニア兼企画職として働く。保険や税制の執筆業務を得意とし、年間約150本の執筆・監修を行う。通信事業者での経験を活かし、通信費削減に関する情報提供にも力を入れる。地域とのつながりを重視し、3人の子育てをしながら「地域×FP」をテーマに空き家問題や創業支援に取り組む。